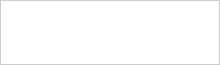2025年度 理事長所信
理事長 小川 祐輝
【スローガン】The Next Generation
〜「狂愚」の精神で時代を切り拓く〜
【はじめに】
私が一般社団法人瑞浪青年会議所(以下、瑞浪JC)の門を叩いたのは、瑞浪JCが創立50周年を迎える2015年でした。その門の中では、40歳までの限られた時間の中で「明るい豊かな社会」を目指し、まちのため、ひとのため、なかまのために自らの生命時間と情熱を思いっきりそそぐ、そんな先輩諸氏の姿があり、その背中を10年間追い続けました。
この先輩諸氏が背中で繋いできた姿は、1965年に瑞浪JC誕生してから今日に至るまでの60年間、世の中が移り変わりメンバーが変わろうともこの姿だけは変わらない、瑞浪JCの根幹をなすものではないでしょうか。先輩諸氏の60年分の圧倒的な生命時間と情熱の上に今の瑞浪JCがあることに感謝し、次世代への歩みを進めていきます。
2025年度スローガン「The Next Generation」には「今までの瑞浪JCを引き継ぎながら進化させる」という想いを込めました。
現代は、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症や、2022年に始まったロシア・ウクライナ戦争といった世界情勢の不安定化、AI(人工知能)をはじめとした急速な技術革新など、変化が激しく複雑で先行きが不透明であり、将来の予測が困難なVUCAの時代と言われています。こうした時代背景がある中で、瑞浪JCに求められている事は、あるべき姿を描くこと、多様性を享受し違いこそが価値になるという組織を築き上げること、正解が無い中で多様なものの見方の可能性に気づき、自ら頭で考え答えを創り出していくことであると考えます。次の10年に向け、瑞浪JCを進化させるきっかけとなる事業を展開してまいります。
【瑞浪JC創立60周年で次世代のあるべき姿を示す】
本年度瑞浪JCは創立60周年を迎えます。創立60周年を迎えるにあたり、10年後に瑞浪がどうなっているのか、瑞浪JCがどういう存在であるべきかを全会員で議論しました。人口減少や消滅可能性都市などの悲観的な話題が多い中で、真に子どもたちが夢や希望を抱けるまちにしたい。そんな瑞浪を心から好きだと思えるまちにしたい。この想いから、瑞浪JCがまちの好循環をもたらす起点となり、瑞浪JCはまちを感動させる存在になるという意味を込め、「さあ、まちを感動させよう」を今年度から10年間の中長期スローガンとして昨年採択しました。
記念すべき創立60周年をお祝いするために、これまで瑞浪JCを創り上げてきた先輩諸氏や支えていただいている関係者をお招きし、これまでの瑞浪JCの活動を振り返ると共に、スローガンを発表しブレない次世代の瑞浪JCの姿を示していきます。
【次世代の「まち」を描く】
瑞浪JCは、本年度より「まちを感動させる」ことに挑戦します。
現在の日本には少子高齢化問題や国際競争力低下など将来に不安を感じさせる課題があります。また、瑞浪市においても同様に人口減少が続き、人口に適したまちづくりをする中で中学校や病院の統合など今まであったものがなくなってしまうことから、まちの将来に対しての悲観的な声も聞こえます。
しかし、悲観的な考えからは、夢や希望を抱ける明るい未来は描けません。「まち」を感動させるためには、思考の箍(たが)を外し、「多様なものの見方」の可能性を感じさせることで夢や希望を抱ける次世代の「まち」を描く必要があります。
また、次世代の「まち」を描くことは、人の心を動かす本質的価値、コミュニティの強化やシビックプライドを醸成する社会的価値、にぎわいを創出したり地域ブランディングにつながる経済的価値をもたらします。
「まち」を構成する多くの人の心を動かし、どんな時代でも夢や希望を抱ける次世代の「まち」を描くプロジェクトを行います。
【次世代へまちをつなぐ】
現在の瑞浪市を見ると、新病院の建設や駅前再開発の推進など、次世代へ向けたまちづくりが進みつつあります。一方で、瑞浪市の20年後の将来人口を見たとき、現在の人口の約4分の3に、15歳から64歳までの生産年齢人口に関しては現在の約3分の2になり、企業誘致をする用地も少ないため税収の増加は見込めず、公共サービスの低下や生活環境の悪化が懸念され、人口減少が加速するという悪循環に陥りかねません。
こうした悪循環を断ち切り次世代に残せるまちをつくるためには、財源を安定させ、まちの発展に向けた好循環を生み出していく必要があります。その財源確保策の一つがふるさと納税です。ふるさと納税制度により、寄附者は自分の想いで納税することができ、自治体は財源になることで市の発展につながり、参加事業者は利益が上がり成長につながります。ふるさと納税額を日本全体で見ると、2023年は前年度を1,521億円上回り1兆1,175億円となり、4年連続で過去最高を更新しており、瑞浪市においても同様に増加しています。また、瑞浪市のふるさと納税額は約2億5,000万円であり順位は全地方自治体の中間あたりですが、上位20%である約350の地方自治体で全ふるさと納税額の約75%を占めており、瑞浪市のふるさと納税額が増加する余地は大いにあると考えます。
次世代にまちをつなぐために、ふるさと納税額の増加に対して行政等と協働し、成功している市町村の事例研究やメンバーが得意とする知見やつながりなど瑞浪JCが持っている資源を活かし、好循環を生み出す起点となりうる事業を行います。
【次世代を担う子どもを育成する】
ここ数年で生成AIが台頭し、非定型な判断処理すら人間の精度を超えてきました。次世代を担う人間に求められていることは、他人軸で決められた枠組の中で自主的に動くことではなく、自分軸で自らの本音でやりたいことを知り、決められた枠がない中で行動を起こすような主体性ある「生きる力」です。
しかし、このような主体性ある「生きる力」を育む環境は少なくなってきています。例えば、少しでも危険なことがあると、大人が先回りし子どもの行動を制限しようとします。また、ゲーム機等で遊ぶことが増え、自然の中で遊びを生み出すような体験をする機会が減っているのが現状です。
このように機会が減ることで、決められた枠組の中では自主的に行動できるかもしれませんが、制限や枠組が無くなった時に主体的な行動やそれに伴う創造性が発揮できなくなります。
子どもたちには、瑞浪でも、日本のどこへ行っても、世界のどこへ行っても、どの様な状況でも主体性を発揮し胸を張って生きてほしいです。作られた枠組みの中で生きるのでなく、枠組みを無くし、子どもたちが自らの意思で主体的に行動し、失敗しようとやってみたいという本音を大切に挑戦できるような機会をつくり子どもたちの主体性ある「生きる力」を育みます。
【次世代の組織をつくる】
瑞浪JCは20歳から40歳までメンバーが活動する団体です。メンバーの職業も経営者、技術者、公務員など様々であり、結婚や子育てなど様々なライフステージにあり、ライフスタイルも様々です。
次世代の組織をつくっていくためには、様々なバックグラウンドを持つメンバーの多様性を享受できる、しなやかな組織環境の構築が必要であると考えています。JC活動と家庭を両立するための育LOMの取り組みを進めると共に、メンバーの個性や多様性がイキイキと発揮できるLOM運営を目指します。
また、表層の多様性だけでなく、さらに一歩踏み込んだ思考の多様性を大切にし、違いこそが価値を生み出すという次世代の組織をつくります。
先行きが不透明で将来の予測が困難な社会となり、答えが無い中で多様なものの見方の可能性に気づき、自ら頭で考え答えを創り出していく思考が求められています。その創り出した考えの違いがぶつかり合うことで組織が活性化し成果を生み出せるようなります。自分なりのものの見方で「自分だけの答え」をつくる思考を学ぶ事業を行います。
【次世代の同志をふやす】
瑞浪JCが60年間運動をし続けられたのは会員拡大があったからです。皆さんは5年前に瑞浪JCが存続の危機となっていたことをご存知でしょうか。この危機を乗り越えた経験が、人の数が組織を活性化させJC運動の強化に繋がる原動力となることを強く思い出させてくれました。存続が危ぶまれる様なことが二度と起こらないように、瑞浪JCの次の10年の活性化につなげていくために、同志を増やすことを重点事項として取り組みます。
会員拡大で一番大切なことは絶対的な行動量です。会員拡大計画の策定を行い、行動の数を増やすための具体策を考え会員拡大を進めます。
【最後に】
「狂愚(きょうぐ)まことに愛すべし、才良まことに虞(おそ)るべし。」
(まるで狂っていると思われるような情熱で常識外れの行動を起こす人間は愛する存在であり、理屈のみで行動しなくなることが最も恐ろしい。)
これは、明治維新で次世代を創る原動力となった人物を多く育てた、吉田松陰が書いた「狂愚」という漢詩の一部です。狂っていると思われるような情熱で、ときには常識という枠組みを外して行動を起こす、この「狂愚」と言う精神こそが、時代を切り拓く次世代を担うリーダーが持つマインドだと考えています。
狂愚の精神で、時代を切り拓く。
これこそが、まちを感動させる我々次世代のリーダーだ。
基本方針
・瑞浪JC創立60周年を祝う事業を行います。
・夢や希望を抱ける次世代の「まち」を描く事業を行います。
・まちづくりの好循環の起点となる事業を行います。
・子どもたちの主体性ある「生きる力」を育成する事業を行います。
・多様性を享受できる、しなやかな組織環境を構築します。
・「自分だけの答え」をつくる思考を学ぶ事業を行います。
・次世代の同志を増やすために行動します。